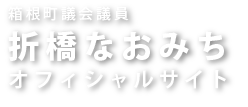視察2日目・室戸世界ジオパーク2013年2月13日
内容
【室戸ジオパーク推進協議会事務局】(2月6日)
室戸市の「アクアリューム」内にある研究室で話を聞くこととなり、室戸市副議長・米澤善吾氏、室戸市議会事務局次長・上松一喜氏、ジオパーク推進課長補佐・杉本健治氏の3名の対応が対応してくれた。
室戸ジオパークは、平成20年6月に推進協議会を設立し、7月にジオパーク認定申請を行い12月に日本ジオパークの認定を受ける。その後21年に世界ジオパークに挑戦するがいずれも選定漏れとなる。22年23年と世界ジオパークへの準備をあらためて行い、24年秋に世界ジオパークの認定を受ける。
「市内22に及ぶジオサイトの保全に係る経費と人的な配置について」
運営体制として、
H21.11.1 室戸市企画財政課にジオパーク推進室(推進協議会事務局:室長1名と担当1名)を設立。
H21.12.1 県職員1名が加わる。
H22.1.4 地質専門員1名と外国語専門員1名が加わる。
H23.4.1 ジオパーク推進課に格上げされ、市職員2名、県職員1名が加わる。
H23.5.1 地質学専門員1名と地理専門員1名が加わる。
人的配置の経過は以上のとおりである。ジオサイトについては人的配置等なく、保全に関してもこれといって特段の手当てはしていない。一度、スプレーによるいたずらがあったが、修繕後は出ていない。
「民間との連携について」
世界ジオパーク認定以前は、市民のジオパークに対する意識が少なく、よく「地質で飯が食えるのか」と言われることが多くあり、市民への周知に苦労をした。幸いなことに、地元の高知新聞がジオパーク認定まで積極的に協力そしてくれ、機会を見つけては経過等の記事を掲載してくれていることも、市民への周知に多くの役割を果たしたこととなる。
「市民への周知と参加について」
人口の減少と少子高齢化が著しく進んでいる状態で、観光としての意識がうすく、ましてジオパークのような、地質学に関することは、殆ど関心を持つような状態ではなかったようである。市民への周知は、より分かりやすい簡単はパンフレットの作成をあげている。なるべく専門的な言葉は少なくし小学生程度が十分に理解できるようなパンフレットを作成する。
市民にはジオパークが「まちづくり」であると理解してもらうように努め、住民の意識を尊重して、みんなで意見を出し合い、ボトムアップ的は発想に転換していった。同時に市民同士の対話を増すような働きかけを行政が行い、関係者の熱意を伝えるように心がけた。
「認定後の外国人観光客の推移について」
特段外国人の観光客が多くなったとは言えないが、それでも今まで全く外国人が来た形跡がないようなところに外国人観光客が来たとのことも聞かれ、効果がないとは言えない。しかし外国人観光客誘客での起爆剤に、ジオパークが大きく寄与することは、あまり期待できないようである。
「観光ガイドの養成について」
平成21年よりガイド養成講座を実施し、現在ガイド登録者は48名となっている。その他「室戸ジオパークマスター講座」を開設。地球科学の知識習得と説明能力向上、受講生が仕事に活用して、来訪者をもてなす。室戸ジオパークの持続的な発展につなげる。
「現地フィールドワーク」
現地のガイドによる説明を聞きながら、フィールドワークを実施するが、フィジーの地震による津波警報が発令されたために、途中で中止となる。
≪室戸の海岸、まさにジオです≫
≪ジオサイトの案内板、判り易く解説二ヶ国語対応です≫
≪植物もジオです。アコウと言うそうです≫
ご意見・お問い合わせ
下記よりお気軽にご意見、お問い合わせをお送りください。